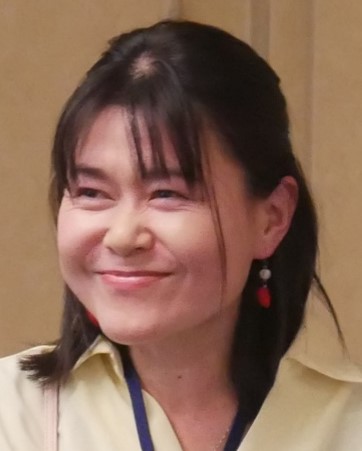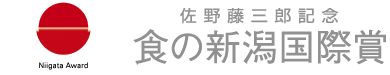受賞者メッセージ
受賞の言葉(各受賞者の職名は受賞当時のものです)
大賞:グントゥール ヴェンカタ スバラオ 氏
国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター 生産環境・畜産領域 主任研究員
この度は、栄誉ある「食の新潟国際賞」大賞を賜り、心より感謝申し上げます。
私たちの研究チームは、2000年から「生物的硝化抑制(BNI)」の研究に取り組んでまいりました。この研究は、農地からの窒素肥料流出問題に端を発しています。調査研究の結果、窒素肥料を栄養源とする土壌細菌が、現代農業で使われる窒素肥料を一方的に消費し、一酸化二窒素や硝酸態窒素に変換され、温室効果ガスや地下水汚染等、環境に悪影響を及ぼしていることを明らかにしました。
私たちは、2003年に植物の根から放出される物質が、土壌細菌を抑制できることを発見し、この機能を「BNI」(Biological Nitrification Inhibition)と名付けました。そして2021年、この「BNI形質」を持つ野生コムギ近縁種(オオハマニンニク)との属間交配により、高収量コムギに導入することに成功しました。
この「BNI強化コムギ」は、窒素肥料の使用量を30-50%削減しつつ、従来品種と同等の収量を実現できます。これは、環境負荷を低減しながら食料生産を維持するという、現代農業の課題解決に大きく貢献する可能性があります。
今後、私たちは「第2の緑の革命」の実現に向けて邁進してまいります。1960年代にノーマン・ボーローグ博士が主導した「緑の革命」から60年以上が経過しており、今日では高い生産効率と環境に配慮した持続可能な農業への転換が求められています。日本で発見されたBNI機能、その技術を応用したBNI強化コムギは、世界の様々なコムギ生産地域で導入準備が進んでおり、「第2の緑の革命」の礎となることが期待されています。
この受賞を励みに、今後も持続可能な農業と食料安全保障の実現に向けて研究を続けてまいります。ありがとうございました。

大賞:ケイト・ケランド 氏
感染症流行対策イノベーション連合(CEPI) 首席科学ライター
この名誉ある賞を受賞させていただき、本当にありがとうございます。
私は、この食の新潟国際賞大賞(グランプリ)が科学ライターやジャーナリストに授与されたのは初めてだと思います。このような素晴らしい賞をいただき、非常に光栄で感謝しております。特に、私の推薦が他のジャーナリストである平沢裕子さんからのものであったことに感謝しています。彼女とは面識がありませんでしたが、私の仕事を読んで評価してくれたのです。
食の新潟国際賞は通常、作物の収量を改善したり栄養価を向上させたりするために画期的な仕事をした科学者や研究者を表彰するものです。これらの仕事は世界中の人々に食糧を提供する助けとなっています。
今回、この賞の選考委員の方々は、科学コミュニケーション、情報、および誤情報が人々の健康に関する意思決定にどれほど重要な役割を果たしているかを時宜にかなった形で認識しています。
私たちは、誤情報が瞬く間に広がり、それが同様に危険である時代に生きています。このため、科学を伝える人々が科学の誠実性を守ることが、私の見解ではさらに重要です。なぜなら、科学に関する誤情報や誤った伝達は、公共の健康に実際の長期的な脅威をもたらす可能性があるからです。ワクチンに関する誤情報がワクチンへの躊躇を引き起こし、予防接種率を低下させ、防げる病気が広がって命を奪うことになることは誰もが知っています。同様に、特定の食品や特定の種類の食事の健康への影響についての主張は、人々を混乱させたり疑心暗鬼にさせたりし、不健康な選択をさせることがあります。
私の一連の調査報道の中心にある除草剤グリホサートの文脈では、科学に関する誤情報や隠蔽が混乱と恐怖を引き起こし、それが個人および公衆の健康に影響を及ぼしています。最終的に、悪い科学と悪い科学コミュニケーションは人々を危険にさらし、政策立案者や個人が誤った決定を下すことにつながります。
この食の新潟国際賞大賞は、科学を適切に伝え、その誠実性を守ることが科学そのものと同じくらい重要であるという非常に歓迎すべき認識だと感じています。改めてありがとうございます。

佐野藤三郎特別賞:八丁 信正 氏
一般社団法人海外農業開発コンサルタンツ協会 会長
近畿大学 名誉教授

この度、栄誉ある食の新潟国際賞佐野藤三郎特別賞を授与いただき、誠に光栄に存じます。この受賞は、これまで私に国際的な活動の機会を与えていただき、支援して頂いた諸先輩方、活動の実施に協力いただいた関係者の皆様のご尽力による賜物であると感じております。ここに深く感謝いたします。また、この賞に推薦いただいた増本教授や審査頂いた選考委員、事務局の方々にも御礼を申し上げます。
国際協力の活動に本格的にかかわったのは、国連食糧農業機関(FAO)での活動だったかと思います。そこでは、農業の水利用の改善、向上を目的として、灌漑水管理に関わる情報のデータベースを作成し、それ用いた統合的なシステム管理とかんがい水管理の改善を図るための情報管理システム(Scheme Irrigation Management Information System: SIMIS)の開発を行いました。また、初心技術者を対象とした灌漑管理訓練マニュアルを作成し、現在でも技術者訓練の実施に活用されていると聞いております。国際水管理研究所(IWMI)理事、理事長の時代には、世界中の水研究者の育成に関与するとともに、他の国際農業研究機関と協力し国際的な農業/水管理に関する研究発展に寄与できたのではないかと思っております。国際かんがい排水委員会では、長年にわたって歴史部会の部会長を務め、世界灌漑遺産事業の立ち上げや審査を支援するとともに、アジアの水の歴史の取りまとめを行いました。
また、国内の国際協力機構(JICA)、国際農林水産業研究センター(JIRCAS)等の事業実施の支援を行う国内支援委員会の委員、委員長として多くの開発事業の円滑な実施に貢献できたのではないかと考えます。
これらの国際レベルの活動に加えて、草の根レベルでの開発活動の支援も行ってまいりました。水関係技術者を会員としたNGO水と大地と緑の会を立ち上げ、会の事務局長として17か国60地区の農村開発活動を支援することが出来ました。また、りそなアジアオセアニア財団の環境事業選考委員として、これまで多くの事業の選考、実施にかかわり、草の根レベルでの環境保全に貢献してまいりました。さらに、近畿大学を中心としたグループと国際協力機構の草の根支援事業をカンボジアで実施し、ため池を活用した乾季農業の普及を支援してきました。
世界の飢餓や貧困の問題に対しては、これまで国連を含めて多くの取り組みが行われてきましたが、その成果は必ずしも十分ではなく、戦争や環境危機と相まって、これらの問題が深刻化しております。こうした中で開発途上国の農村地域における生活水準の向上・地域社会の繁栄・環境の保全の必要性はますます高くなっております。今後は、日本の農業開発コンサルタンツの活動を支援するとともに、草の根レベルでの途上国の農村地域の発展に貢献できればと考えております。

21世紀希望賞:別府 茂 氏
一般社団法人 日本災害食学会 理事・副会長
賞味期間の長さを特徴とする「非常食」という従来の備え方では、乳幼児や食物アレルギーのある児童、高齢者などの食の要配慮者を救えず、また災害救援の従事者にも対応できていないことは、2004年新潟県中越大震災で被災し実感したことでした。この震災を契機に、賞味期間の長さにかかわらずに、災害時にも普段の生活でも活用するという「災害食」が生まれ、その後も続いた新潟中越沖地震、水害などの経験のなかで、災害食の考え方を多くの関係者の皆様から育てていただきました。この取り組み全体が、この度の受賞の大きな意味と感じ、大変感謝している次第です。
この度の受賞により、新しい備え方が被災者の健康を守ることにつながり、また災害多発時代を生きるための新たなライフスタイルとして、全国に拡大するきっかけになること期待しています。さらに災害の多い日本で生まれた「災害食」の考え方が、地球温暖化などにより世界中で増大する自然災害の被災者のために共有され、活用いただくことを目指して、これからも努めたいと思います。

地域未来賞:新谷 梨恵子 氏
株式会社 農プロデュース リッツ 代表取締役
この度は地域未来賞を賜り、大変光栄に感じています。本当にありがとうございます。
私は東京農業大学国際農業開発学科というところを卒業し、今から24年前に小千谷市に嫁ぎました。当時からサツマイモで町おこしをしたいという思いがありまして10年間農業法人で生産・加工・販売の仕事に携わり、9年前に独立、企業しました。
現在は農カフェ経営と6次産業化のプランナーとして新潟県、福島県、群馬県、埼玉県など他県にも派遣していただいたり、農家の営業代理店として農産物を売る仕事。そして、困っている農家さんへの人材の派遣だったり、あと規格外野菜の一次加工といった仕事をしています。
9年前に独立企業した際は田んぼや畑を一切持たずに独立した前例が農業界になく、もがき葛藤した日々だったのですが、今このような場に立てているのは地域の皆さまや応援してくれた方、そして支えてくれたスタッフや家族のおかげです。
これからの農業界や時代を担う若者の支援をしたくて、農業インターンの受け入れや職業体験の受け入れをするために、宿泊施設の完備や農家との連携、農福連携といった形で障害のある方や働きやすい職場環境の整備に努めています。
私自身東京からこちらに嫁いで「小千谷に来たからこそ夢が叶ったんだよ」と言い続けていきたいと思っています。
これから農業界に求められる課題は沢山あると思うのですが、その中でも私にできることや、そしてサツマイモをテーマに色々なことに挑戦していますので、今後もサツマイモや農業界、新潟県全体の農業を盛り上げていけるように頑張っていきます。

地域未来賞:三ツ井 敏明 氏
新潟大学 社会連携推進機構 特任教授
この度、第8回食の新潟国際賞(地域未来賞)をいただくことができ、身に余る光栄であり、関係各位に心から感謝申し上げます。
私は、イネにおける澱粉代謝制御、特に澱粉分解酵素の基礎研究を、生理・生化学的および分子細胞生物学的手法を用いて進めてまいりました。その応用として「高温に強いコシヒカリ」研究に取り組み、新大コシヒカリ(品種名:コシヒカリ新潟大学NU1号)を開発し、社会実装に一歩踏み出すことができたこと、感慨深く感じています。
現在、新潟と東京の大手百貨店や和食レストランで新大コシヒカリ米が提供されています。無論、今回の受賞に至った研究成果を生み出すことが出来たのは、研究の苦楽をともにしてくれた国内外の共同研究者や学生諸氏がいたからこそであることは言うまでもありません。
今後は、このイネ新品種をさらに進化させるべく、耐塩性を含めマルチストレス耐性化させるとともに、これを用いて環境に優しい、地球に優しいコメづくりをテーマに研究開発を推し進めたいと考えています。
また、引き続き、ヨーロッパやアジアの研究者との密接な交流を通じて気候変動下における作物生産向上に貢献すべく、国際共同研究を展開してまいります。

|