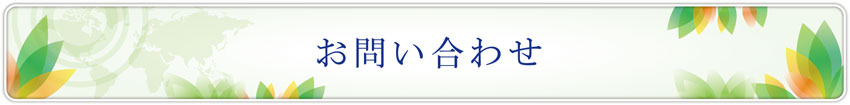増大する飢餓人口や食に起因する健康不安など、世界の食の状況は深刻です。
食料生産や食品産業が盛んな新潟も、食をテーマに世界貢献しようと、食の新潟国際賞を設け、その実現に取り組んでいます。
国際賞は、世界各国から食分野で活躍する個人・団体の推薦を受け、食分野において「世界にとって普遍的な価値を持つこと」「人々の暮らしを救う業績であること」などを原則に選考を進め、「本賞」「佐野藤三郎特別賞」「21世紀希望賞」の3部門で第3回受賞者3名を選定しました。
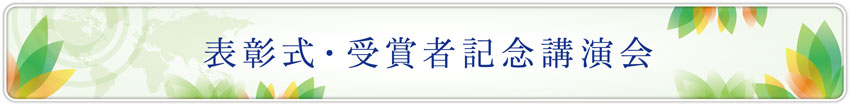
| 日 時 | 平成26年10月29日(水) 14:30~17:00 入場無料 |
|---|---|
| 定 員 | 200名(先着順)事前申込優先 |
| 会 場 | 新潟コンベンションセンター 朱鷺メッセ 4F 「国際会議場」 |
| 配布用チラシ |


本賞
坪井 達史氏(日本)
ウガンダ国立作物資源調査研究所 JICA稲作上級技術アドバイザー
坪井氏は30年間に渡って、アジア・中東・アフリカの開発途上国において稲作技術の指導に携わってきた。前半はアジア各国において水稲を中心に稲作技術を指導した。その後コートジボワールを皮切りにアフリカの活動を行う中で、1990年代半ばに開発された陸稲(ネリカ)のポテンシャルに注目し、2004年以降、ウガンダにおいてネリカ振興のための試験研究や普及に取り組んでいる。氏の技術指導を通じて恩恵を受けたウガンダの農業関係者や農民は1万4千人以上に上る。 同氏は、アフリカにおける稲作の技術開発と普及を実践する世界的な第一人者であり、日本を含む国際社会がアフリカにおいて稲作振興に取り組むにあたり、今後も中核的な役割を果たしていくことが期待される。
1949年12月生まれ。(64歳)

佐野藤三郎特別賞
C・L・ラクシュミパティ・ゴウダ氏(インド)
国際半乾燥熱帯作物研究所(ICRISAT) 副所長
ゴウダ博士は過去37年間に亘って、高収量と抗立ち枯れ病や、抗オオバコ対策に重点を置きながら、ヒヨコマメの改良開発研究に携わってきた。
博士と彼のチームは、進んだ品種系列を開発し、これを世界中の30カ国供給した。
この品種素材を基礎にして、10カ国の発展途上国の科学者たちが、68種類の高収穫品種を開発する事ができた。これらの品種の多くは農家の収入向上や国家のGDPに対して、目覚ましい貢献となった。
ゴウダ博士はアジア13ヶ国が参加する「アジア穀物豆類アジアネットワーク(CLM)」のコーディネーターとして共通の目的である「アジア農民の生活を改善するために、それぞれが目指す作物の生産性と生産量の向上」に向かって各国研究者と連携しながら現在も積極的な活動を続けている。1949年6月インド生まれ。(65歳)

21世紀希望賞
中井 博之氏(日本)
新潟大学農学部自然科学研究科 助教
自然界には多種多様なオリゴ糖が存在しており、そのそれぞれが独自の機能性・利便性を有しているが、多様性に富むオリゴ糖のそれぞれの単一で低コスト大量調製が困難なため、現在産業的に利用可能なオリゴ糖はごくわずかである。
中井博之氏は、ホスホリラーゼという自然界に存在する安全な生体触媒である糖質関連酵素を活用して、ヒトの健康保持増進に有益な機能性オリゴ糖のバリエーションを大幅に拡大(200種類以上)。さらにデンプンやセルロースなどの植物性バイオマスまたカニやエビなどの甲殻類の外骨格を形成するキチンなどの海洋性バイオマスを、高付加価値な機能性オリゴ糖に高収率変換する革新的な低コスト汎用製造技術の開発に成功した。
1977年10月生まれ。(36歳)
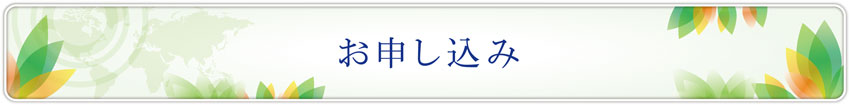
| はがきの場合 | 送付先:
株式会社 アド・メディック 〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山3丁目9-6 |
|---|---|
| FAXの場合 | FAX:025-247-8101 (チラシをダウンロードしご記入の上、送信してください。) |
| E-mailの場合 | award@niigata-hatsu.com (氏名/所属・役職/住所/TELをご記入ください) |